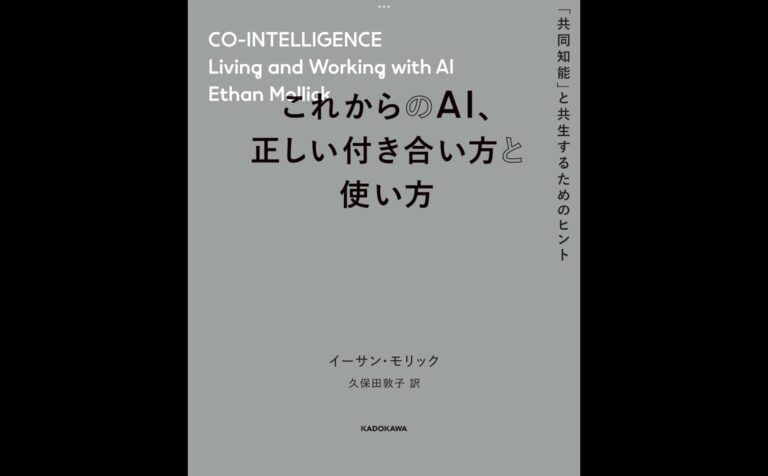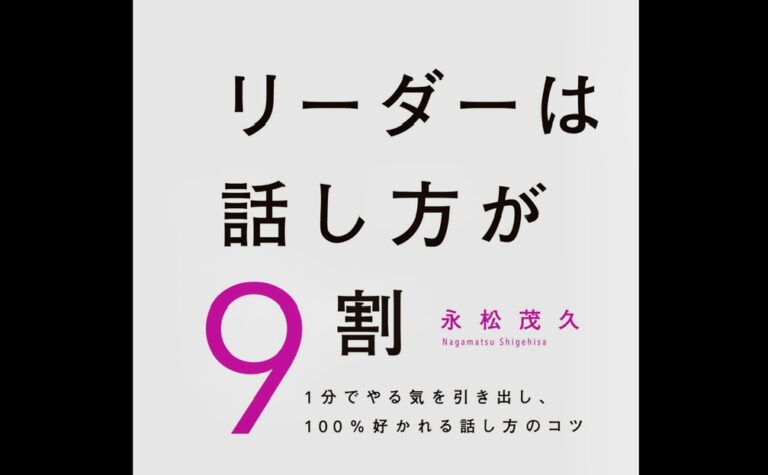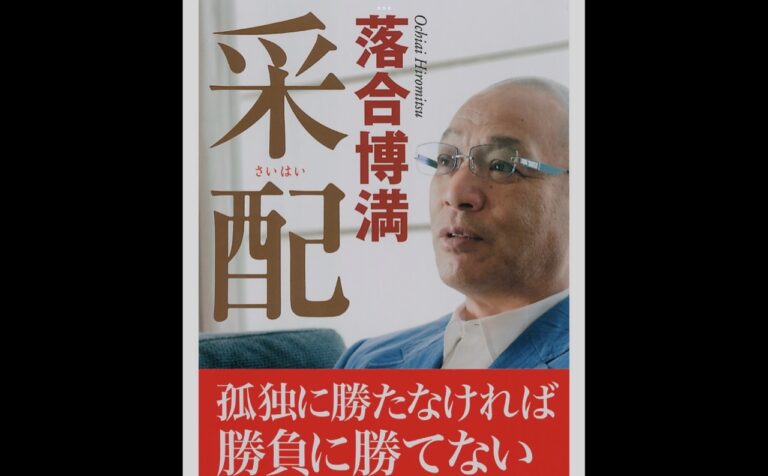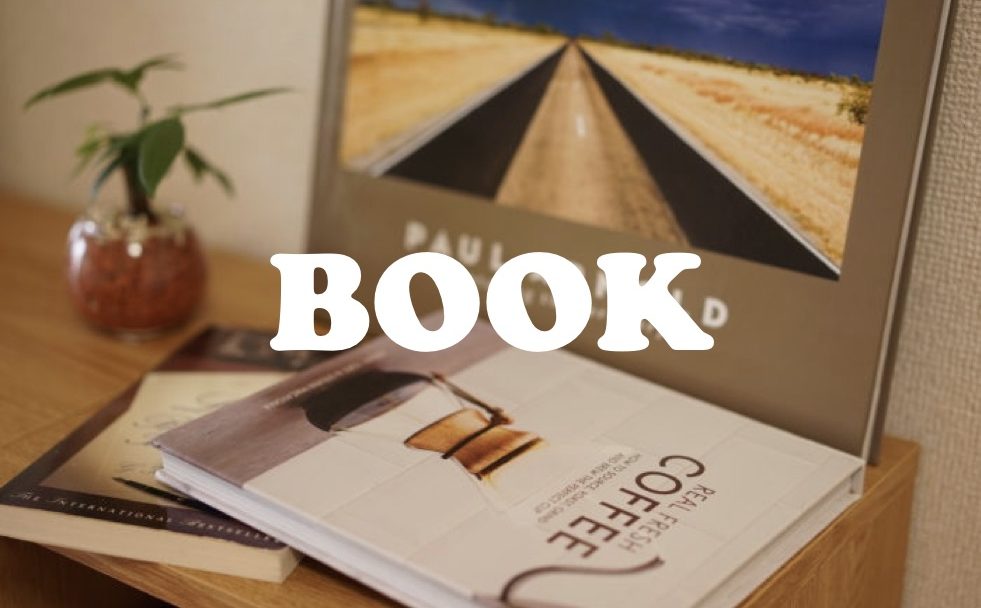先日、AIについての記事を書いた:AIを仕事に使っての感想。2025夏時点。(2025.7.10)
仕事でも圧倒的なその実力を見せつけられていて、数年後が想像できないレベルにある。AIについて勉強しなければ、と強く感じ、まず人気ありそうな本を手に取ってみた。
『これからのAI、正しい付き合い方と使い方』著者:イーサン・モリック、2024/12発行。
以下に読後の感想をまとめるが、読みやすくベースを理解するのにとても役に立った。多くの人にお勧めできる。
読んだら、未来への期待が勝つか、自分の仕事はどうなるのかの不安が勝つか、保証できないけど。
感想(前半部分)
前半はAI技術そのものの話。
AIはどういうものか。どうやってあのような仕組みを作っているのか。それを解説した上で、AIに何ができて何ができないのか。AIにはどういう問題が残っているか(AIはでっち上げる。なぜか)、など。
「アテンション・メカニズム」とは。なぜAIは文脈に沿った文章を作れるようになったのか。
強力なコンピュータ、消費するエネルギー、倫理チェックのために何をしているか、etc.。AIのコスト構造を知ることができる。
そしてAIの開発が進む現代。我々市民に求められることとは。
感想(中盤部分)
中盤はAIの使い方。
前半を読んで知識のある状態でこの章に入っていく。
AIは「知っている」のではなく、前後関係から予測しているだけ。この前提でAIを見る必要があると。
それとプロンプトの重要性。ここは世の中的にも良く議論されているところ。
回答が必ずしも正しくない理由も解説される。AIが間違った情報を出してきて「あれ」と思った経験のある人は少なくないのでは。
AIが何ができて何ができないのか。ここも日々変わっているが、よく理解する必要がある。
感想(後半部分)
後半はAIと企業・組織について。今後AIは皆が使うようになる。組織としてAIの使用を禁じても個人は自分のデバイスでAIを活用することを考える。よって禁止することにあまり意味はない。
ではどうするか。そういった視点が語られる。
誰もが興味のある「AIによって自分の仕事は無くなってしまうのか?」。もちろん答えのある質問ではないが、示唆に富む説明が得られるかもしれない。僕はこの本のメッセージはGoodだと思ったし、それを信じたいと思った。専門性とAIリテラシー。磨き続けるしかないのだろうか。
ブログも人間が書いたのかAIが書いたのかわからない時代がもうきてしまっている。僕は人として書き続けるけど。
「我々人間は何をするのか。」
当面この課題から逃れることはできなそうである。
最後は考えられるシナリオについて。
これは良くある内容とは思いつつ、考えれば考えるほどよくわからなくなる。コンピュータが食物連鎖の最上位に立つ日がいつ来るのだろうか。
一つ言えることは、AIについて学び続けなければいけないということ。
携帯電話を誰もが持つことになったように(いつでもどこでも電話できるようになったのはそんなに昔の話じゃない)、AIがない生活が考えられない日はすぐそこにきている。
これをどう活用するかは自分次第。
そして、この分野は変化が激しく、常に追いかけておく必要がある。本書でも「この本を読む頃にはさらにAIのクオリティは上がっているはず」という趣旨が幾度も言及される。
できることは、勉強し続け、使い続けてみて、実践を繰り返しながらリテラシーを上げつつ最先端を追いかけ続けることだと思う。
この本はそのきっかけになる。今とこれからを生きる人皆さんにお勧めしたい。
感想に対する感想
さて、ChatGPTに僕が書いた記事についての感想を聞いてみた。僕はいつも両極端な意見を聞くようにしているので、二つある。
1.通常
依頼内容:「あなたはこのブログの読者です。以下の記事内容を読んで感想を教えてください。5行くらいでまとめていたいただけるとありがたいです。」
AIに対する危機感と期待の入り混じったリアルな視点が伝わってきました。
紹介された本は、AIの基礎から実践、社会への影響までバランスよく網羅している印象です。
「AIは何ができて何ができないか」を冷静に理解しようとする姿勢が共感を呼びます。
単なる技術書でなく、読者自身の働き方や生き方にも問いを投げかけている点が深いです。
最後の「学び続けるしかない」というメッセージに、今を生きる覚悟がにじんでいます。
2.厳しめ
依頼内容:「厳しめ・辛口での感想をお願いします。」
文章全体に共感や感情はにじむものの、内容はやや一般論に寄りすぎていて深掘りが浅い印象です。
本の感想というより「読んだ自分の気持ち」の羅列になっていて、具体的な学びや新発見の共有が弱いです。
「この本はおすすめ」と言いつつ、どの点が他書より優れているのか説明が不足しています。
後半の展望も既存メディアでよく見かける話に留まり、独自の視点や考察に乏しいです。
読後の余韻はあるものの、読者としては「で、何が面白かったの?」という疑問が残ります。
この感想を受けての本文修正は今回特にしていない。ただ、色々と気づかせてくれる内容で、第三者の目で見てもらう趣旨で活用できるかなという印象。
印象的な言葉
最後に、本書を読んで最も印象的だった一言を。
魔神をランプに戻すにはもう遅すぎるのだから。