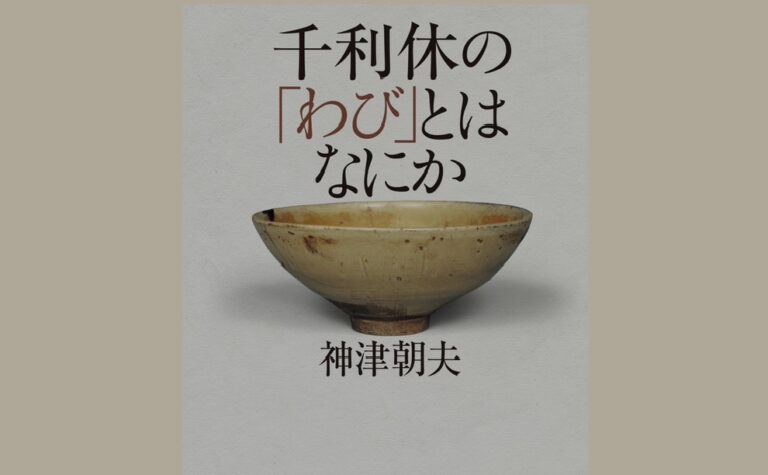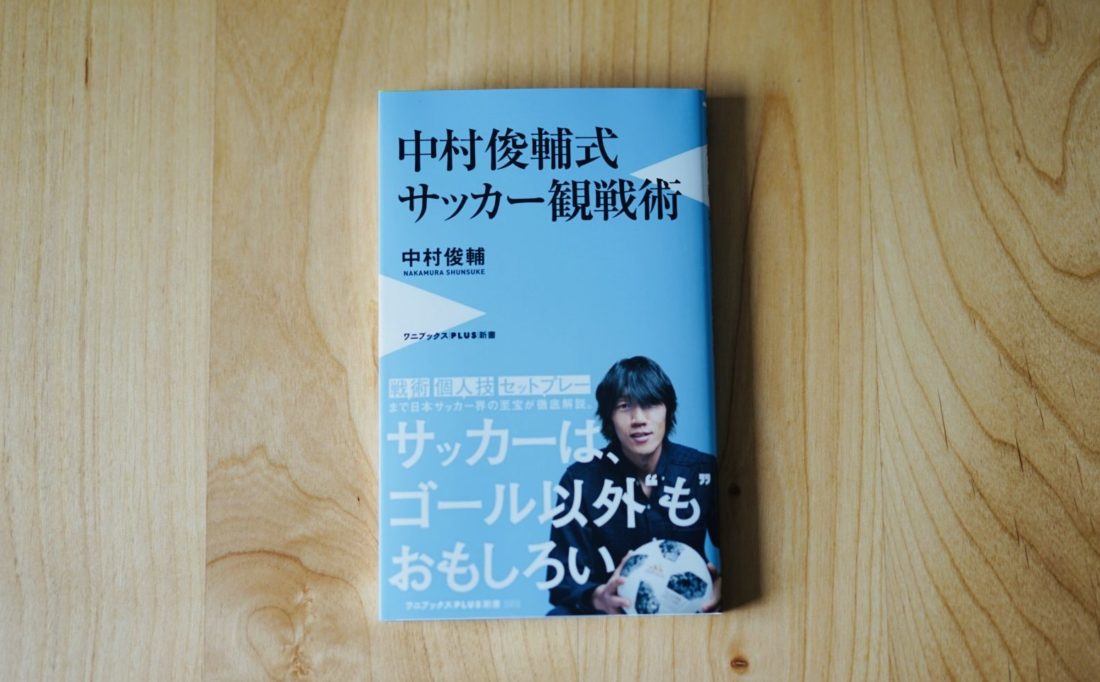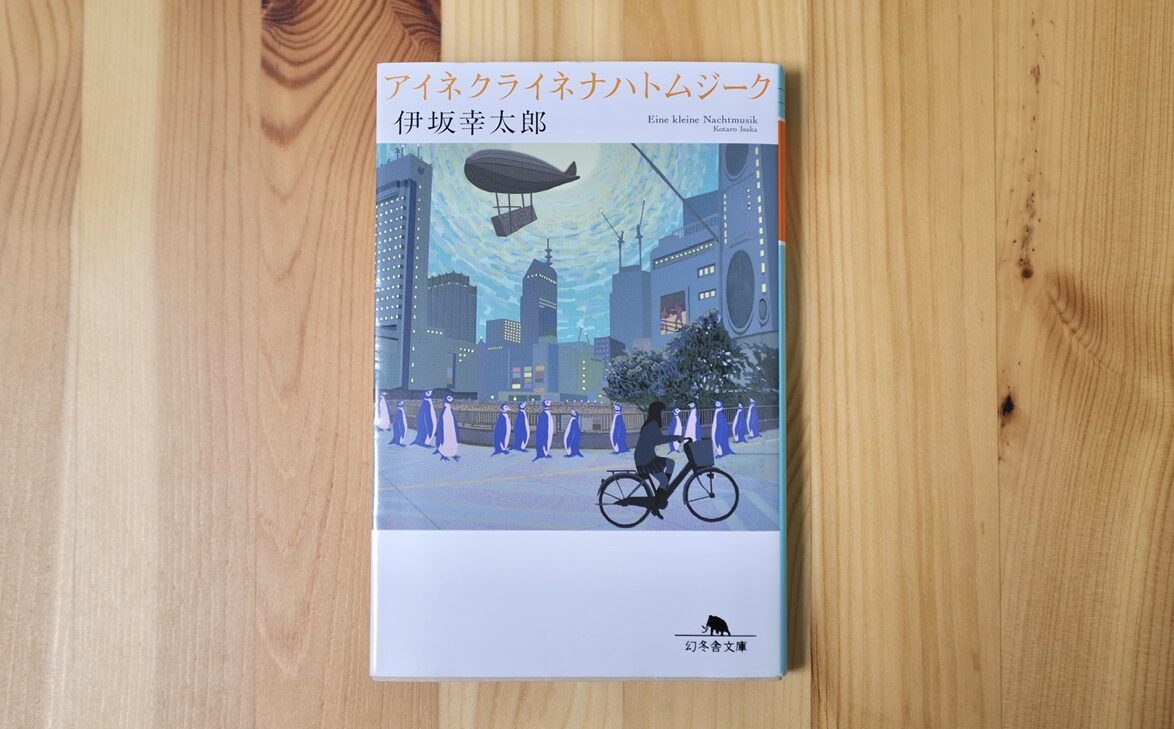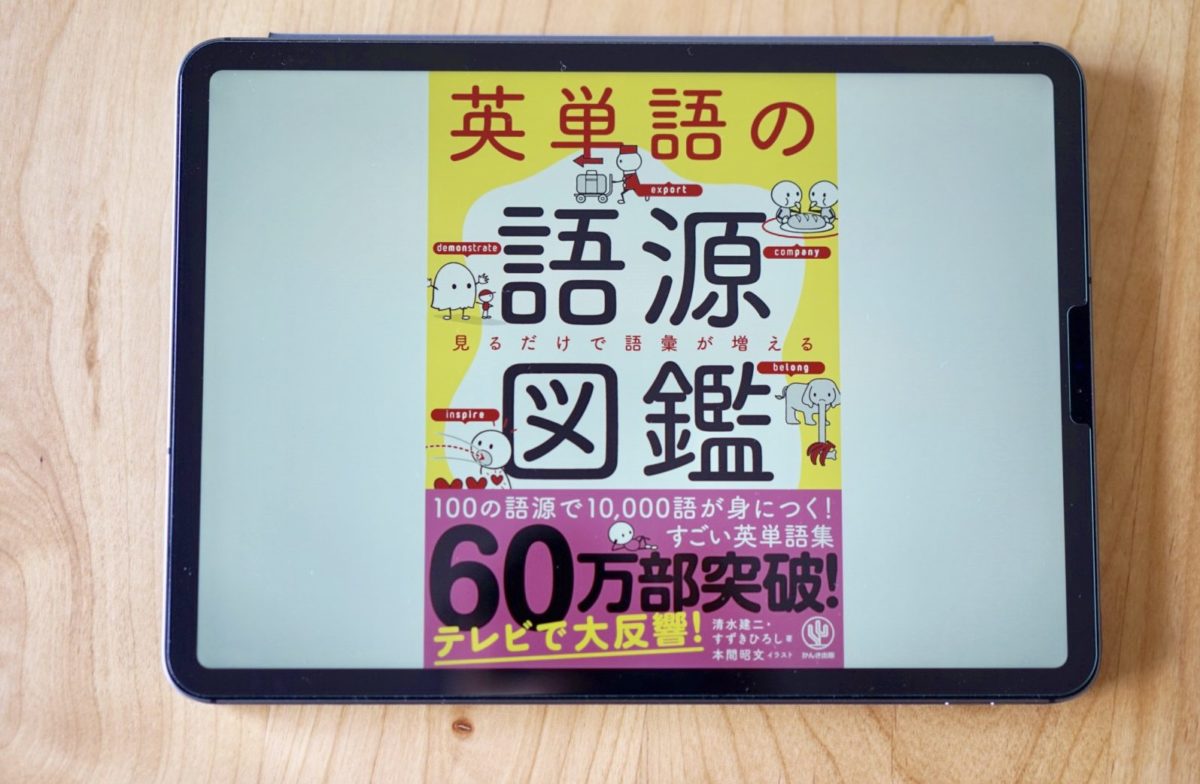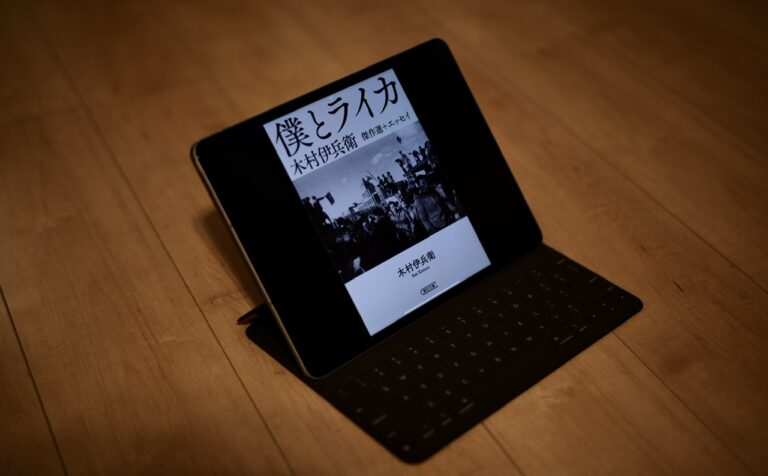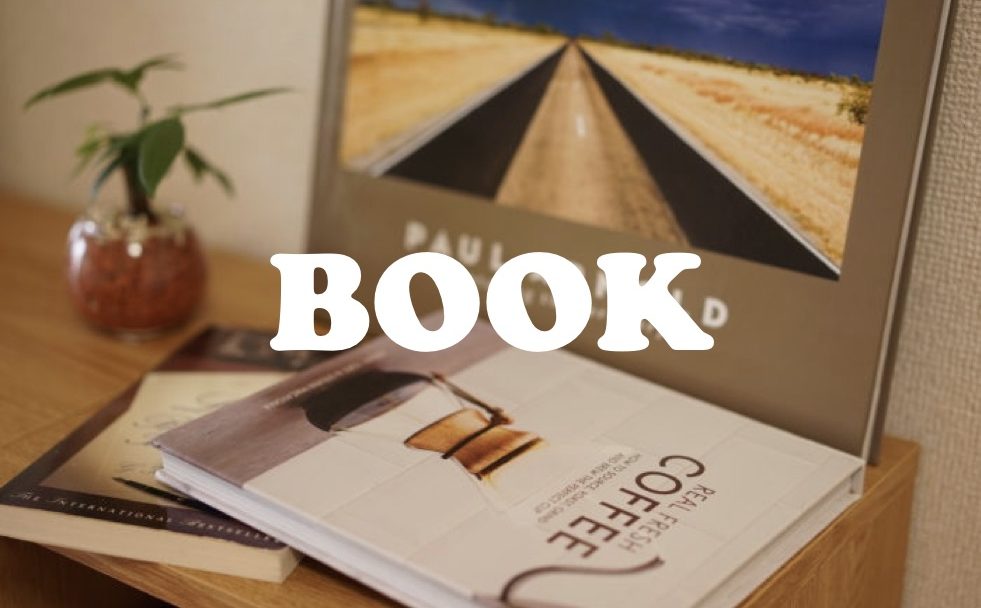以前こんな記事を書いた:家は漏らぬほどにて足ることなり(千利休)
これがきっかけで、千利休について学びたいなと思い、購入したのが『千利休の「わび」とはなにか?』という本。
第一章は、千利休について 、誰が書いたどの文献をどう解釈するか、についての解説が主。事実はなんなのか、そのものにフォーカスし説明が進んでいく。
しかし本書は論文チック。引用も多いが、引用される文章は、~候。や…を以て先となし、とかその時代の言い方で頭に入ってこない。。。
また利休の師弟は誰だったのか、どのような道具を使っていたか、など過去の文献等をもとに分析されるのだが、これまた中身や名前含め頭に入ってこない。
本書の根拠として重要な部分であり省けないことを理解しつつ、本質だけをなんとか拾うべく読み飛ばせそうなところは読み飛ばしながら読了。
後半1/4あたりからわび茶についての考察・文章が増える。茶室の配置や向き、構造などは面白かった。この本は茶の歴史も深く洞察されていて、日本の文化の大事な部分を学べる。
茶室の実物を見に行きたいなと思った。
しかし、大半が理解できなかったのは事実、かつ本書を多くの人にお勧めできないのも実感。素人ながら通しで読み、素直な感想としてメモしておく。深くこの世界を学びたい方には貴重な一冊なのだと思う。僕に教養がないだけかもしれないが。。。
知らない世界はあるものだな、というのが改めての学び。