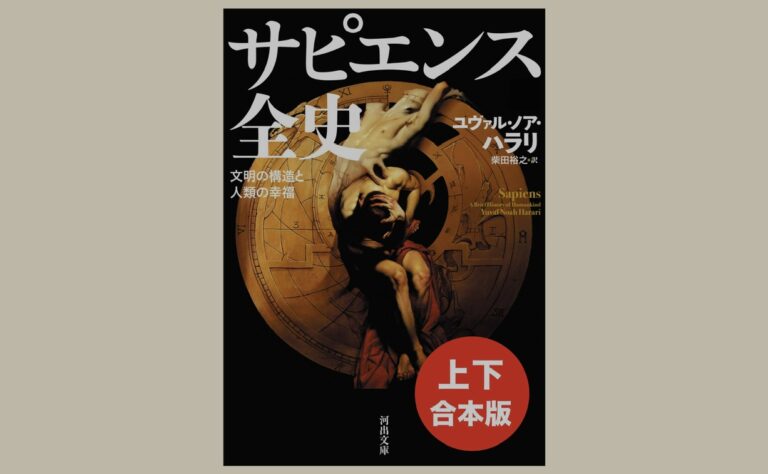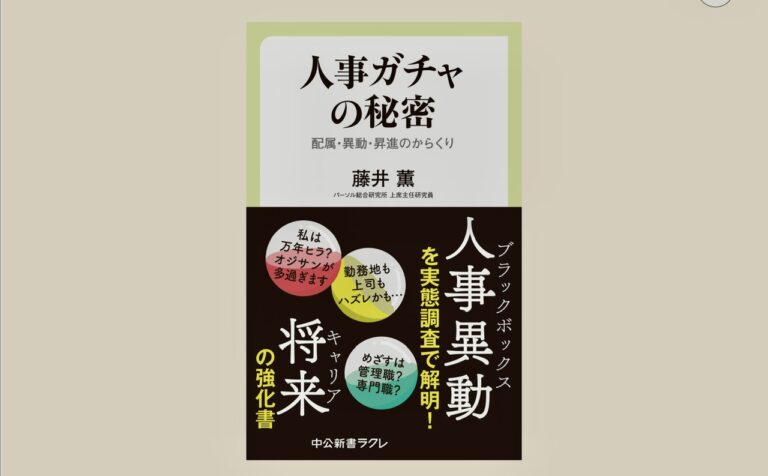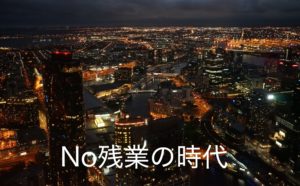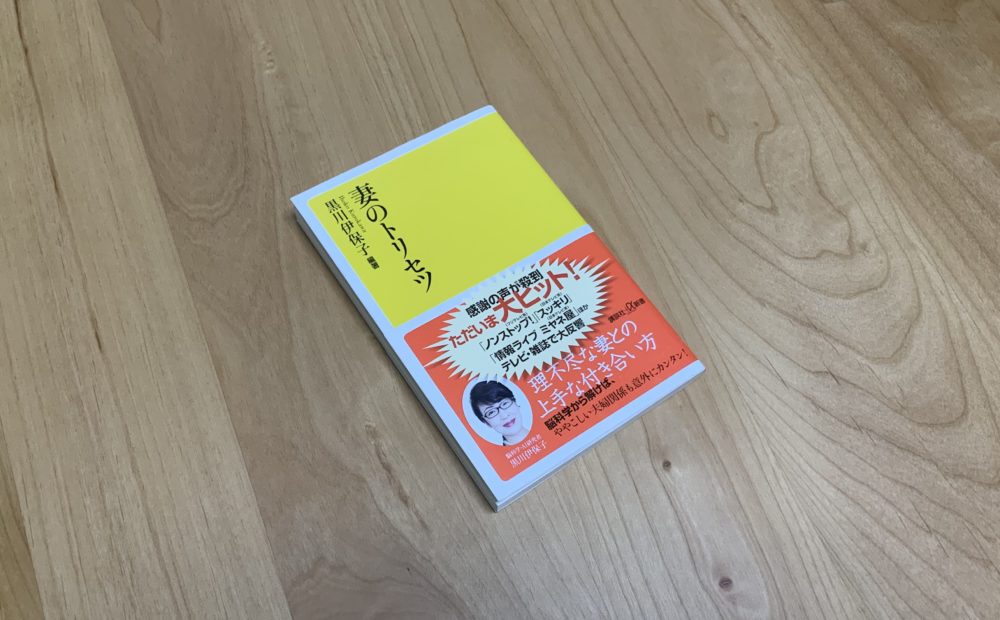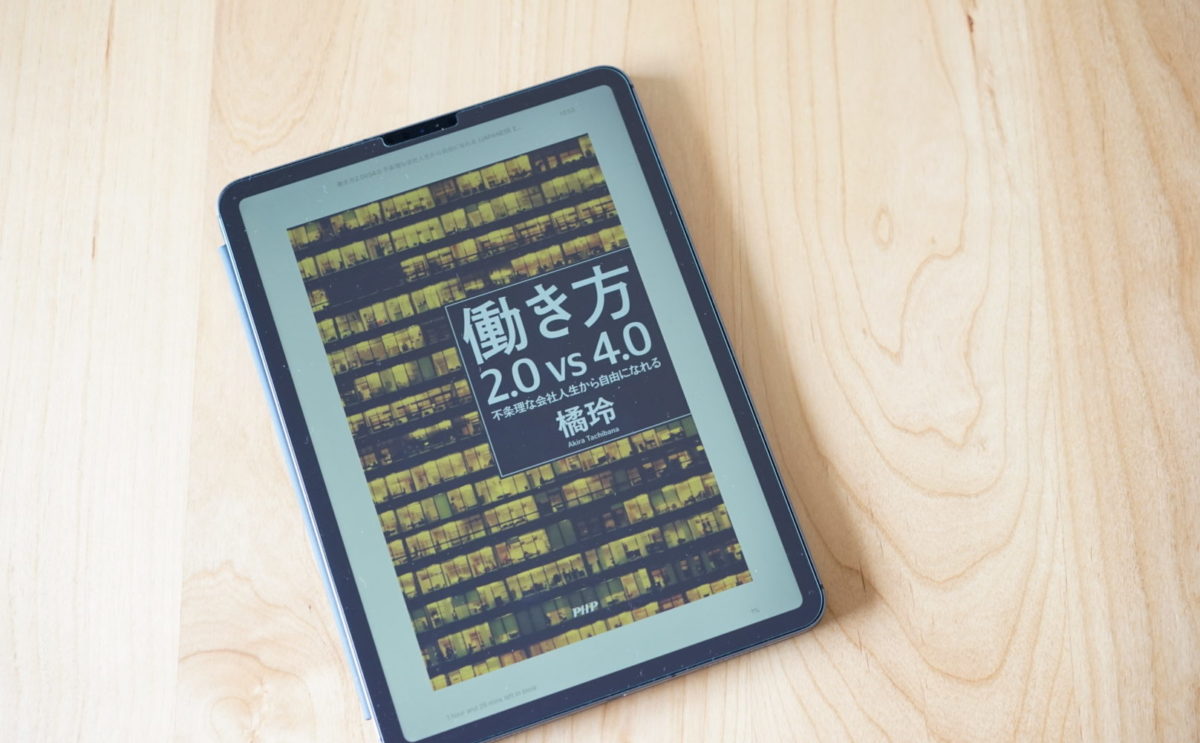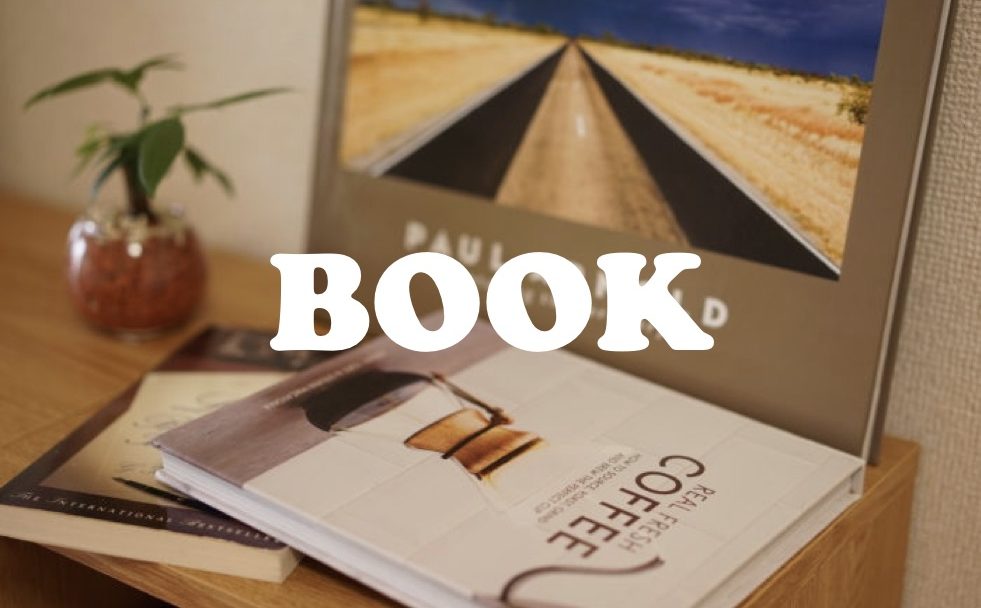哲学の本、宗教の本、歴史の本、地理の本、経済の本…どうカテゴライズしてよいかわからない。
著者ユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』を読了した。
我々人間はどこから来たのか。何者なのか。
昨今AIの進歩がすさまじく、人はどう生きるべきか迷う時代はもうすぐなように思われる。
そんなとき、考え抜き、哲学を持って生きることが大事になるのではと考える。
本書は、人類の起源からいま、そして将来への言及まで語られる。ぜひ多くの人に読んでいただきたい一冊。多くの気づきや学びを得られるはず。
僕がこれまで読んだ本の中で、最も多くのマーカーを引いたかもしれない。それくらい勉強になったし、もう一度ポイントをおさらいしたいと思った。
以下、読んでのメモを簡単に残しておきたい。
本書からの学び
今当たり前と思うことは当たり前ではない。太古の昔にそんなものはなかった。今あるものには発明された理由がある。
それらの流れが語られており、とても勉強になった。
数学や科学はもちろん、宗教や貨幣、法人といったものは古代にはなかった。確かに。
法人(Corporation)とはなにか。なぜ法人がでてきたのか。とても興味深い。なるほど、と。
人類には信じるものが必要だった。多くの人がまとまるために。貨幣最も成功したものの一つらしい。
続いて牛や豚や鶏について。分かってはいたが文字にされると響くものがあった。牛や豚や鶏は進化の点では成功している。絶滅のリスクは小さく、地球全体にかなりの数の仲間が存在する。しかし彼ら彼女らは幸せなのだろうか。
ベルトコンベアで流されるたくさんのひよこの写真。個人的にはなかなかこたえた。我々がやっていることは正しいのか。
上巻の後半、下巻あたりから宗教の話題が中心となる。キリスト教、仏教の本質とは何か。なぜそれらは生まれたのかの考察が読める。仏教のところの考え方は、この本を読んで初めてしっくり来た気がする。何を悟るのか。「足るを知る」の本質。
資本主義も宗教の一部ではないか。何が違うんだと。
技術、資本主義、それらが歴史に果たした役割。なぜヨーロッパが世界を制したのか?
ジェイムズクック船長はなぜオーストラリアに向かったのか。

無知を認めることの重要性。無知を認めるからこそ探検、探索に勤しむ。
「無知の自覚」が比較的新しいというのは衝撃だった。中世は、皆全て知っている、という前提だった。なぜコロンブス大陸じゃなくてアメリカ大陸と呼ばれるようになったのか。コロンブスは東アジアの大陸だと思いそこの人をインディアンと呼んだ。アメリゴ・ヴィスプッチはその大陸を知らない大陸だと考え、地図を作った。その流れからアメリカと呼ばれるようになった。
スペインによるアステカ帝国、インカ帝国の征服。ヨーロッパの人たちが世界を征服しようとした力。英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、etc.とアフリカや南米、アジアで使われるのはなぜか。
言語学も重要なんだと理解した。その土地をヨーロッパから来た少ない人数で支配するには、現地の言葉や文化を理解することが重要だった。
ヨーロッパの人たちは、知らないことを認め、新しい知識に価値があることを知っていたと。今でも世界のルールはヨーロッパの人たちが先行するイメージがある。日本から見るとうまくやられてしまうように見える。この流れは今にも通じているのかなと感じた。
そして近代。

資本主義とは何か。
「信用(クレジット)」の活用。富の総量が増えるという前提。だから信用取引を使って融資できる。未来が明るいから、お金を貸す、お金を貸してもらえるから事業を開始でき、お金を返せる。全ては未来を信じることが始まり。
利益が得られたらまた投資する。自分の利益が他の人の利益にもなる。資本主義の本質。なぜ経済成長を目指すのか。この本を読んで理解できた気がした。
目指さないと「信用」を活用した好循環が得られないのだ、と。タンスの貯金を引っ張り出そうとする人たちの論理がここにあるのか、と改めて勉強になった。本書は説く。動物や食料の総量は増えない。価値を増やすのは科学であると。新しい何かを科学が生み出すのを世界は待っている。バブルが弾けないようにお金を刷りながら。
なぜ科学研究に投資するのか?科学と戦争。
エネルギーに対する洞察も興味深かった。
そして後半、今後サピエンスはどこに向かっていくのか。今どのようなことが起きているか。幸せとは何か。我々の技術は我々を幸せにしているのか。深い難題が続く。
この本を読んでから世界を回ったら景色の見方が変わるだろう。人間の歴史と物語が浮かび上がってくるかもしれない。本書は、世界史であり、地理であり、宗教・哲学の本であり、科学の本であり、経済の本であり、etc…。とにかく幅広い。サピエンスを理解するために、全て繋がっていることを読みながら実感した。これらは中学高校で別科目として学ぶが、全てが密につながっている。そんなこと学校で教わった気がしないが、この本を読んだら高校の勉強もより面白くなるかもしれない。
本書は「なぜそうなのか」の根拠をできるだけ追い求めようとしているのがいい。また諸説ある場合はそれぞれを挙げてくれるのもいい。世界史の教科書もこれくらい面白いと良いのだが。
Kindleでは、上・下通しで購入することができる。かなりボリュームがあるが読む価値がある。
世の中の動き、や我々のルーツに深い洞察を与えてくれる一冊。どうやって本書に出会ったかすでに思い出せないものの、面白そうな本はないかな、と探し続けることの大切さを改めて認識した。
ヘブライ語版は2011年、英語版は2014年に発行されている。文庫版あとがきにはその後も10年も添えられている。
現在2025年。AI。予想された速度よりはるかに早く自ら意思決定できるツールが実用化されつつある。
自分の生きる価値は何か、何をよりどころに生きるのか、考え続けないと。さもなければAIに大事なものを奪われるだろう。それを考えるにあたって、この本は導入として良いかもしれない。
これからの時代思った以上に哲学が重要になってきそう。
関連記事
- これからの「正義」の話をしよう、という本の紹介。哲学を学ぶことが重要な時代になってきたと感じる。(2020.4.27)
- 僕の「哲学」との出会い。学ぶことを勧める理由(2020)
- 歴史や地理、政治を学ぶ理由(2024.1.16)